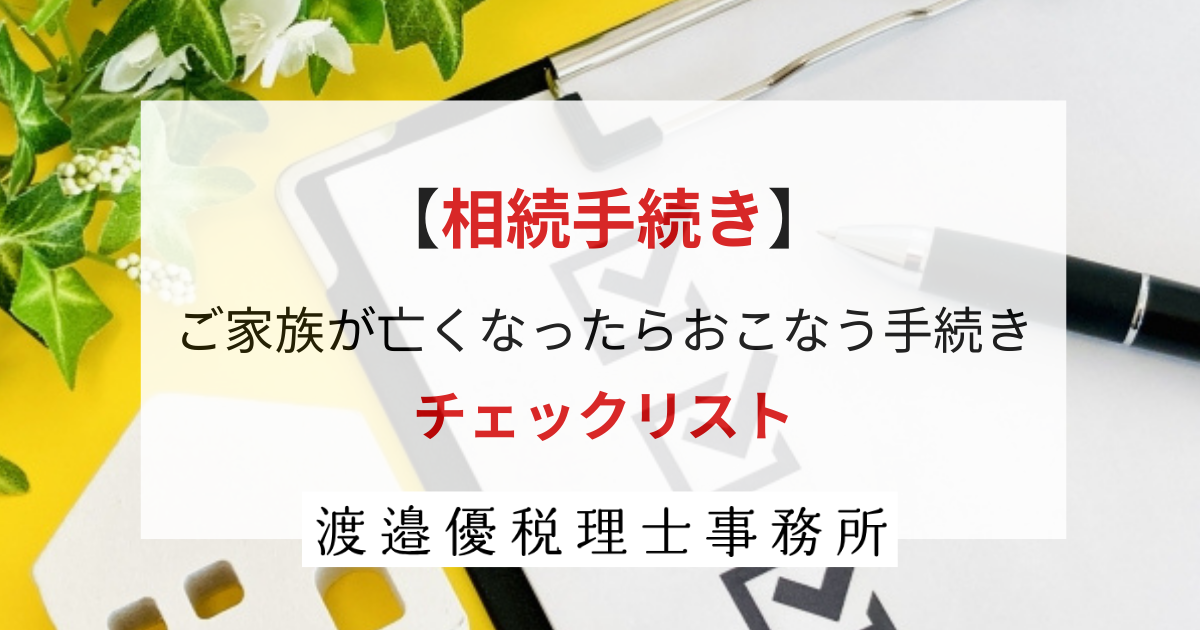
大切なご家族が亡くなった後、残された方には「やること」がたくさんあります。
まず思いつくのはお葬式の準備ですが、実は、それ以外にも思いのほか多くの手続きがあるのです。
本記事では、相続手続きで「何をするか」「いつまでにやるか」「どこに行けばいいか」をまとめています。
初めてのことで何から手をつけたらよいかわからない、提出期限がせまっている等の不安がある方はぜひご活用ください。
チェックリストをもとに、一つずつ手続きを進めていきましょう。
目次
まずは「期限ごと」に、一般的な相続手続きをチェックリストで確認しましょう。なお、区役所や市役所、町村役場をまとめて「区役所等」としています。
期限が早く到来するものから、優先して取り掛かることが重要です。
相続手続きは、その多くが今までに経験のないことや専門的な知識が必要なことばかりです。不慣れななか、すべての作業を一人でおこなうことは難しいかもしれません。
統計上、相続税申告は全体の約86%の方が税理士へ依頼しています。ご自身で申告をおこなう方は、約14%と少数派です。
「令和4事務年度国税庁実績評価書 : 財務省」(財務省)を加工して作成
相続手続きで困ったら、税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの資格を持った専門家に相談できます。
相続の専門家は、本人の代わりに手続きをしたり話し合ったりすることもできますが、専門業務としてその専門家にしかできないこともあるので確認しましょう。
相続争いの解決は弁護士にしかできませんが、相続争いがなければ税理士や司法書士に相談するとスムーズです。
当事務所には税理士・司法書士が在籍しているほか、弁護士等の他の専門家との連携もできるため、トータルでのサポートが可能です。
相続手続きは作業が多く専門知識を要するため、ご家族を亡くしたばかりの方への負担は相当なものです。
専門家へ依頼することで、スムーズかつ確実に相続手続きを進められます。日常生活を守るためにも相続手続きを一人で抱え込まずに、早めに専門家に依頼することをおすすめします。
ここから、各項目の手続きについてわかりやすくご紹介します。まずは、死亡日から7日~14日以内におこなう相続手続きです。
死亡診断書(死体検案書)は、死亡を証明するための書類です。
診療を受けていた方が病院で亡くなった場合には「死亡診断書」として、診療を受けていなかった方が死亡した場合や死体に異常がみられる場合等には「死体検案書」として、病院や介護施設から発行されます。
一般的に、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体になっており、右側が「死亡診断書(死体検案書)」で医師が記入する場所、左側が「死亡届」でご家族が記入します。
法務省「死亡届」を加工して作成
なお、死亡診断書(死体検案書)は再発行できません。相続手続きに必要になることもあるので、必ずコピーを取っておきましょう。
死亡届は、死亡から7日以内に、死亡者の死亡地(または本籍地)か届出人の所在地の区役所等へ提出します。
死亡届の提出と同時に火葬許可証の交付申請をおこない、区役所等から火葬許可証が発行されます。火葬許可証は火葬の際に必要なので、紛失しないよう注意が必要です。
訃報はできるだけ早く、親族や知人・友人等の故人と縁の深かった方へ連絡をします。
故人の死亡日時、死因(簡単に)、葬祭日時(決まっていれば)等をお伝えしましょう。電話で連絡をするのが一般的ですが、相手との関係性によってはメールやSNSで伝えることもあります。
ご家族が亡くなった後にできるだけ早く、葬儀社へ連絡をしましょう。ご遺体の安置場所への移動や、保管などのサポートをしてもらえます。
その後、葬儀の日程や場所を決め、葬儀の詳しい内容を話し合います。一般的には、お通夜・告別式・火葬の順に葬儀が進みます。
すべての国民は「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」のいずれかの健康保険に加入しています。
死亡したら、被保険者の資格が喪失するため脱退の手続きが必要です。医療機関等の清算が終わっていれば、このタイミングで健康保険証の返却もしましょう。
会社員は、協会けんぽまたは健保組合の健康保険に加入しており、死亡日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
会社は、死亡から5日以内に「被保険者資格喪失届」を年金事務所等に提出しなくてはいけませんので、死亡後は速やかに故人の会社へ連絡をしましょう。
また、故人に被扶養者がいる場合、被扶養者も社会保険の資格を喪失します。そのため、国民健康保険への加入や、他の家族の被扶養者になるといった対応が必要です。
自営業者は、国民健康保険や国保組合に加入しています。
国民健康保険の場合、区役所等へ死亡届を提出すると同時に健康保険から脱退することになるケースと、死亡届とは別に死亡から14日以内に脱退の手続きが必要なケースがあります。
自治体により対応が異なりますので、故人の住民票があった自治体の区役所等へ確認してください。
また国保組合の場合は、死亡届とは別に、死亡から14日以内に各国保組合へ「資格喪失届」の提出が必要です。
75歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入しています。
後期高齢者医療保険の場合も、区役所等への死亡届のみで保険の脱退も同時におこなわれるケースと、死亡から14日以内に故人が住んでいた住所地の区役所等へ「後期高齢者医療資格喪失書」を届けるケースがあります。
死亡届の提出時に確認しましょう。
亡くなった方が年金を受給していた場合、原則として「年金受給者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
厚生年金や共済年金の場合は死亡から10日以内に、国民年金の場合は14日以内に年金事務所または年金相談センターへ、年金証書と死亡が証明できる書類(住民票除票や死亡診断書のコピー等)とともに年金受給者死亡届(報告書)を提出します。
なお、故人が日本年金機構へマイナンバーの収録をしていれば、区役所等への死亡届提出をすることで日本年金機構への死亡報告も済んだことになるので、改めて年金事務所等への書類提出は要りません。
介護保険被保険者証は、65歳以上の方または40歳以上65歳未満の要介護(または要支援)認定を受けた方などが交付を受けています。
故人が介護保険被保険者証の交付を受けていた場合は、故人の住民票があった自治体の区役所等へ死亡から14日以内に「介護保険の資格喪失届」を提出し、介護保険被保険者証を返却します。
世帯主の方が死亡した場合、死亡から14日以内に区役所等に対して「世帯主変更届」の提出が必要です。
なお、世帯主以外に同世帯だった方が1人しかいない場合には、自動的にその方が世帯主になるため届出は必要ありません。
ご家族が亡くなった後に絶対にやってはいけないことが「遺言の開封」と「遺産の使い込み」です。
ご自宅などから故人の遺言が発見された場合、決して開封してはいけません。
自宅などで見つかった遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、遺言の内容を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きです。
家庭裁判所での検認手続きをせず遺言を勝手に開封すると、改ざんや隠蔽行為が疑われるだけでなく、5万円以下の過料に処される場合もあります。
遺産分割の前に、勝手に故人の遺産を使い込むことも絶対にやってはいけません。
遺産分割が終わるまでは、故人の預金などの遺産は相続人全体のものだという意識が必要です。もし遺産を使い込んだり、使い込みを隠したりした場合、損害賠償請求をされる可能性もあります。
ここまでが「死亡から7日~14日以内におこなう相続手続き」です。ご家族が亡くなった直後に一人でこれだけの相続手続きをするのは大変な作業です。早い段階から専門家へ相談することも検討してみましょう。
死亡日から1カ月~2カ月以内におこなう相続手続きを紹介します。
健康保険証をまだ返却していない場合には、早めに返却しましょう。健康保険証の返却は、葬祭費や埋葬料の申請要件にもなっています。
国民健康保険証または後期高齢者医療保険証は、故人の住民票があった自治体の区役所等へ返却します。
健康保険証は、故人のものだけではなく被扶養者の分も返却します。返却先は、故人の勤務先です。
故人が生前に加入していた健康保険からの給付として、一定額の葬祭費(または埋葬料)が支給されます。支給額は、自治体や加入する健康保険により異なります。
葬祭費等を受け取るには、申請が必要です。申請期限は葬祭から(または死亡から)2年ですが、葬祭が済み次第、領収書などの添付資料とともに申請をおこないましょう。
〈葬祭費(または埋葬料)の申請先〉
故人の銀行口座に遺された金銭を保護するために、金融機関へ口座凍結の連絡をします。
口座凍結をすることで、キャッシュカード等を利用した遺産の使い込みや口座の不正使用を防ぐことが可能です。口座凍結のための必要書類は金融機関により異なるので確認してください。
故人の住居を使用する予定がない場合、水道光熱費や通信費等の公共料金の解約手続きが必要です。
引き続き故人の住居を使用する場合は、名義変更の手続きをしましょう。検針票や利用明細書などから契約会社や契約番号を確認できます。電話やホームページから解約または名義変更の手続きをしましょう。
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。故人が遺した遺言書が1通だけとは限りません。最も新しい遺言書に効力があります。
次の3ヵ所を確認しましょう。
(1)自宅や貸金庫等から見つかる可能性があります。故人の部屋や仏壇、タンス、金庫等を探してみましょう。また、信頼できる方に遺言書を預けていることもあるので、思い当たる場合は確認が必要です。
(2)「自筆証書遺言」は法務局へ預けることができます。法務局へ「遺言書保管事実証明書」の請求をして遺言書の有無を確認してください。
(3)「公正証書遺言」を作成していた場合は公証役場で遺言書の原本が保管され、正本や謄本は本人へ交付されています。正本や謄本が見つからない場合は、公証役場で遺言の有無を調べましょう。
自宅で自筆証書遺言が見つかった場合、決して開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きをして、遺言書の存在を明確にする必要があります。なお、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認の必要がありません。
検認の申立には申立書、故人の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など複数の書類を添付しなくてはいけません。添付書類が揃うまでに時間がかかることも予想されるため、早めの対応が必要になるでしょう。
遺産分割や預貯金の払い戻し等には相続人全員の同意が必要なので、相続人が誰なのかを明確にしなくてはいけません。ここで問題になるのが、ご家族が知らない相続人(以前の配偶者との間の子、異母兄弟等)がいるかもしれないということです。
事実を客観的に証明するために、以下の戸籍謄本が必要です。
(1) 故人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
(2) 相続人全員の戸籍謄本
(1)・(2)すべての戸籍謄本の内容を確認して、相続人を確定させます。
「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」は、どちらも故人と相続人との関係性をまとめたものです。一般的に「相続関係説明図」は手続きの数が少ないときに任意で作成されます。
「法定相続情報一覧図」は法務局に申請する公的な証明書として、相続関係説明図よりもさまざまな手続きに対応できます。
どちらも絶対に必要なものではありませんが、作成しておくことで不動産の相続登記や預金口座の名義変更などの相続手続きがスムーズに進みます。
相続関係説明図については【自分で簡単に作成】相続人の関係が整理できる相続関係説明図の作り方で詳しく説明していますのでご覧ください。
遺産分割をするにあたって故人の財産調査が必要です。現金や預金、不動産、株式、生命保険などのプラスの財産だけでなく、借金や税金の未払いなどマイナスの財産もすべて洗い出して、評価額を明確にします。
財産調査に漏れがあると、遺産分割のやり直しや相続税の申告漏れなどにつながるので、慎重な調査が必要です。
財産調査のポイントは、次のとおりです。
いずれの調査も不慣れな方には難しく、時間を要することがあります。
特に、不動産の評価方法については「相続税における不動産の評価方法を簡単にわかりやすく解説!!」で説明しているとおり、専門知識を要します。
当事務所は「不動産相続に強い税理士事務所」です。相続や不動産に関するお悩みがある場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
遺産分割協議は相続人全員が参加のもと、遺産を誰にどのように分けるかを話し合う場です。故人の財産調査の結果をふまえて、遺産分割協議に入ります。
遺産分割には、相続人全員の合意が必要です。話し合いがもつれて全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停や審判へと移る可能性もあります。
遺産分割協議で決定したことをまとめたものが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、すべてに相続人の署名と実印による押印をして一通ずつ保管します。
遺産分割協議書は必ず作成するものではありませんが、不動産や預金の名義変更手続きに必要になったり、相続人間での争いを防いだりするため作成したほうがよいでしょう。
なお、遺産分割協議書の作成方法は「【文例つき】不動産の相続登記に必要な遺産分割協議書の書き方を紹介!」で解説していますので参考にしてください。
遺言や遺産分割協議により預貯金や不動産を相続することが決まったら、預貯金は各金融機関で、不動産は法務局で名義変更手続きをします。
「遺言書があるケース」と「遺産分割協議書があるケース」で必要書類は異なるため、注意しましょう。主な必要書類は、次のとおりです。
預貯金は金融機関ごとに必要書類が異なるため、あらかじめ問い合わせをして書類を揃えてから手続きをしたほうがよいでしょう。
なお、相続により取得した不動産の名義変更を「相続登記」といいます。
相続してから3年以内に相続登記をすることが義務付けられていますが、名義変更をしていないと不動産を売却できない等の不都合が生じる恐れがあります。はやめに手続きを済ませましょう。
不動産の名義変更には、他にも必要となる書類があります。詳しい手続きや必要書類は、法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」をご確認ください。
闘病生活の末にご家族が亡くなった場合、高額療養費制度によりいったん支払った医療費を払い戻しできる可能性があります。所得や年齢等により医療費の自己負担額上限が定められており、上限を超えて支払った金額の払い戻しを受けられます。
高額療養費は健康保険から給付されるので、加入していた健康保険の団体(協会けんぽ、健康保険組合等)へ問い合わせをして請求をしてください。
死亡日から3カ月~4カ月の相続手続きを紹介します。
故人が遺した財産を相続するかどうかの選択肢として「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。
相続放棄と限定承認は、ご家族が亡くなってから3カ月以内に申し立てをしなければなりません。どちらも多額の借金がある場合に利用されることが多いので、なるべく早く財産調査をする必要があります。
なお、相続放棄と限定承認の手続きには、複数の添付書類が必要です。詳しくは、裁判所ホームページ相続の放棄の申述 、相続の限定承認の申述をご確認ください。
準確定申告とは、故人が1月1日から死亡日までの間に得た所得について、本人に代わりご家族がおこなう所得税の確定申告をいいます。
準確定申告の期限は、死亡から4カ月以内です。そのため、故人が死亡までの間にどれだけの収入等があったのかを、はやめに把握しましょう。
なお、準確定申告については「相続が発生した場合の準確定申告とは?申告が必要な場合のポイントを解説」で詳しく説明しています。
相続放棄や限定承認、準確定申告は聞き慣れない用語や書類の提出が必要です。どちらも期限があるので、難しいと感じたらはやめに専門家への相談をご検討ください。
死亡から1年以内におこなう相続手続きを紹介します。
遺言書や遺産分割協議により決定した内容にもとづいて、実際に相続人で遺産を分けます。名義変更が必要な預金や不動産、株式、自動車等を相続した場合は、名義変更を済ませましょう。
相続税の申告は、死亡から10カ月以内です。納税も死亡から10カ月以内で一括納付が原則なので、相続税額が多額の場合には、不動産売却や納税のための借入れなど納付方法の検討も必要になるでしょう。
相続税額の計算は、すべての相続財産の洗い出しと相続人の確定をしてから手続きに入ります。特例を活用することで、相続税を抑えることも可能です。
遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内です。配偶者・子・父母には、状況により遺留分を請求する権利があります。
具体的なケースで確認しましょう。たとえば、被相続人が父、相続人が配偶者・長男・次男の3人である場合に、父が次男に1円も相続させないと遺言書に記載したとしても、次男が遺産を最低限もらえる権利を主張して請求することが可能です。
その他にも、相続手続きはまだまだあります。一つずつ終わらせていきましょう。
生命保険や共済などに加入していた場合、死亡保険金が給付されます。故人が契約していた保険会社や共済組合へ死亡の連絡をして、保険金を受け取るための手続きをしましょう。
死亡保険金の請求期限は死亡から3年ですが、死亡保険金は相続税の課税対象なので、財産の洗い出しと同時期におこなうとよいでしょう。
故人名義のクレジットカードは、利用停止手続きが必要です。
クレジットカード自体が発見できなかったとしても、口座からカード利用料金が引き落とされていて利用が確認できる場合は手続きをしましょう。利用停止の手続きをしないと、不正利用や年会費を払い続ける等の危険性があります。
故人の運転免許証の返納は義務付けられてはいないため、返納しなくても問題ありません。しかし返納しない場合、運転免許証更新の通知が届きます。
通知を止めたい場合には、警察署や運転免許センターに返納の手続きをしましょう。
パスポートは、名義人が死亡した時点で失効し返却することが義務付けられています。各都道府県のパスポート申請窓口に、戸籍謄本等の死亡したことがわかる書類とともに返却をしてください。
株式を相続した場合、株式の名義変更が必要です。
上場している株式を証券会社を通じて購入した場合は、一般的には証券会社を通じて名義変更がおこなわれます。上場していない株式(家族の会社や知り合いの会社の株式等)は、その会社に直接連絡をして手続きを進めましょう。
デジタル資産とは、ネット銀行の預金、ネット証券で購入した株式や投資信託、暗号資産、プリペイド式電子マネー残高等、パソコンやスマートフォンで管理する金銭等のことです。
デジタル資産の相続には、IDやパスワードが必要です。もしIDやパスワードがわからないときは、ネット銀行やネット証券等に問い合わせましょう。
故人が所有していた自動車を引き続き利用する場合は、名義変更をしましょう。戸籍謄本等の必要書類を用意して、各都道府県の運輸支局で手続きをする必要があります。
自動車を利用しない場合、そのまま所有し続けると毎年自動車税が課税されますので、売却や廃車等、処分を検討しましょう。
預貯金を相続した場合「故人の口座を解約して払い戻しする」方法と「相続人に名義変更する」方法の2つがあります。
どちらも、準備する書類や手続きはほとんど変わりません。遺産分割の状況等をふまえて、いずれかの方法を選択して手続きを進めてください。
ある程度の相続手続きが済むまでは、故人の携帯電話やスマートフォンが必要になることがあります。手続き上、故人の知人の連絡先や、取引内容を確認することがあるためです。
大切なデータは保存し、一連の手続きが完了してから契約している携帯会社へ連絡して解約手続きを進めましょう。
雑誌の定期購読や、動画や音楽の配信サービス等のサブスクリプション契約があれば、解約または名義変更の手続きをしましょう。
口座の取引明細やクレジットカードの請求書等から、サブスクリプション契約を見つけることが可能です。解約や名義変更の手続きをしないことで、毎月(または毎年)利用料が発生しますので注意しましょう。
相続手続きに関するよくある質問をまとめました。それぞれ詳しい記事がありますので、ぜひご覧ください。
相続人が認知症や障害者である場合、生前に故人が何かしらの対応策をとっていた可能性があります。
詳細は「相続人が障害者なら備えておこう!生前にできる対策を徹底解説!」「【親が認知症の疑い?】認知症による税金のトラブルと対策方法を解説!」で説明していますので、ぜひご覧ください。
相続人に未成年がいる場合、遺産分割協議に特別代理人を選定したり相続税の計算をする際に未成年者控除を受けたりと特有の手続きが必要になります。
詳しくは「未成年者の相続はどうする?相続税の未成年者控除と特別代理人を徹底解説」で説明していますのでご覧ください。
葬式費用は、相続税計算の際に課税財産から控除できます。どのような費用が葬式費用の対象となるのか詳しく解説していますので、「相続税で控除できる葬式費用はどこまで?チェックリスト付き完全ガイド」をご覧ください。
相続した家屋等が空き家になる場合、売却時に使える特例があります。売却するとかかる税金を軽減できる特例については「【税負担を大幅軽減】相続時の空き家3,000万円控除の利用方法を解説!!」で詳しく説明しています。
故人が海外に持っていた資産を相続した場合、日本と海外で相続税を二重に納めていることがあります。この場合、外国税額控除を利用することで、海外で納めた相続税を日本の相続税から控除可能です。
要件や対象となる可能性のある国等について「【海外に財産がある場合は注意】外国税額控除で二重課税を回避する方法」でまとめていますので、海外の資産を相続した方は参考にしてください。
本記事では、親や家族が亡くなった際に必要な手続きを「チェックリスト」にまとめました。
相続手続きは多岐にわたり、それぞれ期限も異なるため「何をするか」「いつまでにやるか」「どこに行けばいいか」を期限ごとに整理して一つずつ進めていくことが重要です。
相続は、多くの専門的な手続きを伴います。一人で抱え込まずに、税理士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに関するご相談を承っております。税理士・司法書士が在籍しており、弁護士や土地家屋調査士等の専門家とも連携しているので、トータルでのサポートが可能です。
相続手続きについてお困りのときは、以下の問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
