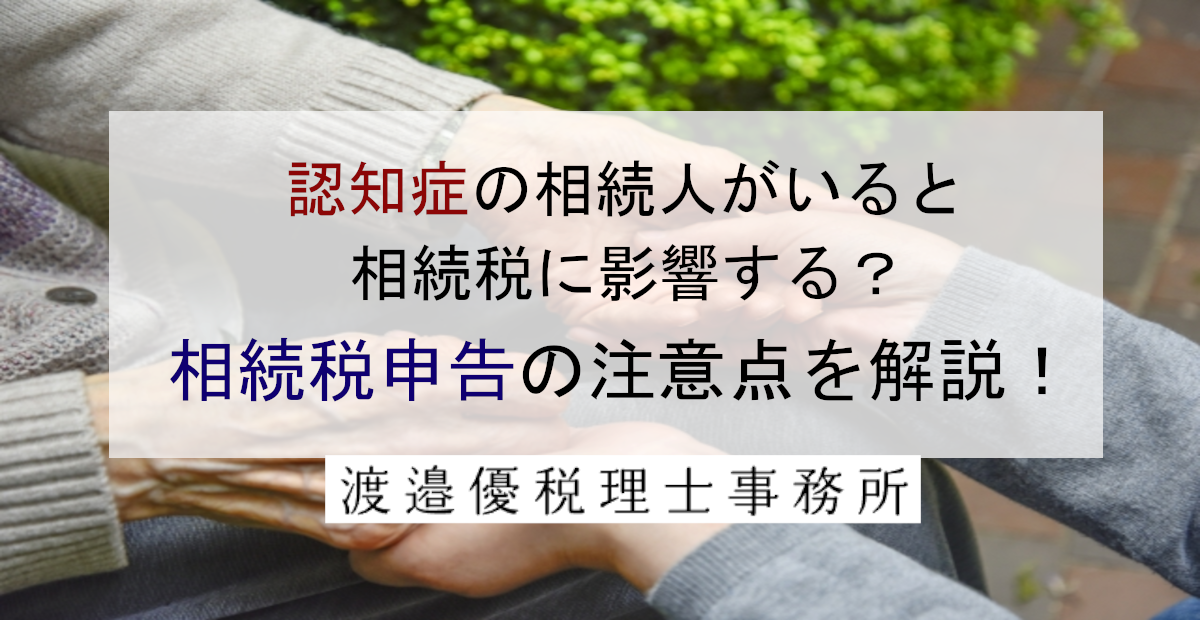
「相続人の1人に認知症の親がいるが、相続手続きは大丈夫だろうか?」「相続税が高くなってしまうのではないか?」
高齢化が進む現代では、このような不安も少なくありません。ただでさえ複雑な相続手続きですが、相続人の中に認知症の方がいる場合は、通常とは異なる対応が求められ、相続税申告にも影響を及ぼす可能性があります。
ここでは「相続人に認知症の方がいる場合に起こりうる問題点や相続税申告への影響、具体的な事前の対応策」について詳しく解説します。
目次
認知症とは、脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下してしまい日常生活に支障が出ている状態のことを言います。認知症によって「意思能力(自分の行為の結果を理解し、判断する能力)」が不十分な方が相続人にいる場合、相続では主に3つの大きな問題が生じます。
遺言書がない相続では、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める「遺産分割協議」が必要になり、遺産分割協議は「相続人全員の合意」がなければ法的に成立しません。
認知症で意思能力が不十分と判断される相続人がいる場合、遺産分割協議に参加して有効な意思表示(同意)をすることができないため、遺産分割協議を法的に成立させることはできません。たとえ他の相続人全員が協議に同意していたとしても、認知症の相続人を除外した協議は無効になります。
遺産分割協議ができなければ、相続財産は実質的に「凍結」状態になってしまいます。
預貯金は、被相続人の死亡を金融機関が知ると口座が凍結され、遺産分割協議が成立するまで凍結されます。葬式費用などに充てるための「預貯金の仮払い制度」がありますが、引き出せる金額には制限があります。
不動産については、遺産分割協議が成立しない場合は法定相続分による相続人全員の共有名義になります。共有名義の不動産を売却したり、賃貸に出したりするには共有者全員の同意が必要ですが、共有者である認知症の相続人は同意することができないため、実質的に動かすことができない凍結状態になります。
遺産や負債の一切を相続しないことを選択する「相続放棄」も本人の意思能力が必要な法律行為であるため、認知症の相続人は自ら相続放棄をすることができません。
相続人に認知症の方がいることで遺産分割協議が進まないと相続税申告において「未分割のリスク」が生じます。
相続税申告は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」の申告期限が設けられており、この期限内に遺産分割協議が整わなければ財産を誰が相続するか決まっていない「未分割」で申告せざるを得ません。
相続税を未分割で申告する場合、ひとまず法定相続分に従って各相続人が財産を取得したと仮定して相続税額を計算し、納税することになりますが、相続税額を大幅に軽減できる特例を適用することができないため、税額が大幅に増加してしまう可能性があります。
相続税には、税額を抑えることができる様々な特例がありますが、その中でも「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」は税額を大幅に軽減することができるため非常に重要な特例です。
未分割申告の最大のデメリットは、相続税額を大幅に軽減できるこの2つの特例が適用できないことです。
【配偶者の税額軽減】
配偶者が財産を相続した場合に、相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」までであれば、相続税が非課税になる節税効果が高い制度です。しかし、未分割の状態では配偶者が相続する財産が確定していないため、配偶者の税額軽減は適用することができません。
【小規模宅地等の特例】
被相続人の居住していた宅地や事業に使用していた宅地などを相続した場合、その宅地の相続税評価額を最大80%(貸付事業用宅地等は50%)減額できる制度です。この特例についても、未分割である場合は誰が対象の土地を相続するか決まっていないため、特例を利用することはできません。
※なお、未分割での申告であっても「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、申告期限後3年以内に分割が成立すれば、特例の適用を受けるための手続き(更正の請求)が可能です。
詳しくは「遺産分割が間に合わない時は未分割申告が必要|未分割申告に必要な分割見込書とは?」をご覧ください。
未分割の状態で特例が利用できないと相続税はどれくらい増加するのでしょうか。具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
◦ 被相続人:父
◦ 相続人:母(認知症)、子1人
◦ 相続財産:自宅土地(330㎡以下、評価額1億円)、その他財産(評価額1億円)、合計2億円
◦ 遺言書なし
※遺産分割が成立した場合は、母が自宅土地とその他財産の一部(自宅土地とその他財産を合計して全財産の50%)を相続するものとします。
遺産分割が行われ、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」の特例が利用できた場合の相続税額は580万円になります。
・小規模宅地等の特例により自宅土地1億円×(1-80%)=2,000万円
・自宅土地2,000万円+その他財産1億円=1億2,000万円
・相続税の総額=(1億2,000万円-基礎控除4,200万円)÷2人=3,900万円
3,900万円×税率20%-200万円=580万円 580万円×2人=1,160万円
・配偶者の税額軽減後の相続税1,160万円-580万円=580万円
特例が利用できない場合の相続税は、法定相続分での計算になるため3,340万円になります。
・自宅土地1億円+その他財産1億円=2億円
・相続税の総額=(2億円-基礎控除4,200万円)÷2人=7,900万円
7,900万円×税率30%-700万円=1,670万円 1,670万円×2人=3,340万円
上記のケースでは、特例が利用できる場合と未分割のため特例が利用できない場合との相続税額の差は実に2,760万円になります。相続人に認知症の方がいる場合は、遺産分割ができず、これほど大きな税額の差が生じてしまう可能性があります。
ただし、配偶者の税額軽減は二次相続のことも考慮して適用しなければ不利になってしまう場合もあります。
相続人に認知症の方がいる場合、法的に遺産分割協議を進める唯一の方法が「成年後見制度」の利用です。成年後見制度とは、家庭裁判所に申し立てを行い、認知症の方の財産管理や契約などを代理で行う「成年後見人」を選任してもらう制度です。成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することで、法的に有効な協議を成立させることができます。
成年後見制度は、認知症の相続人がいる場合に有効な方法ですが、他の相続人の都合や節税を目的とした柔軟な遺産分割が認められないケースも少なくありません。また、家庭裁判所への申し立てから後見が開始されるまで時間がかかります。相続税申告期限が10か月であることを考えると迅速な手続きが必要になります。
後見人に弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合には費用が発生し、専門家が後見人である限り払い続ければならないため、金銭的な負担も生じることになります。
相続時に認知症の相続人がいると、手続きは複雑になり、金銭的・精神的な負担も大きくなります。そこで最も重要で最善の解決策は「生前対策」です。
最も有効で基本的な対策は「遺言書を作成しておくこと」です。 有効な遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言の内容に従ってスムーズに相続手続きを進めることができます。これにより、相続財産の凍結や未分割申告といった問題を根本から回避することが可能です。
近年注目されている制度が「家族信託」という制度です。 この制度は、元気なうちに信頼できる家族(子など)に財産の管理・処分を託す契約を結ぶ制度です。
信託契約によって、親が認知症になった後でも、託された子などが契約内容に従って不動産の売却や預金の管理を継続することができるため、資産凍結を防ぐことができます。成年後見制度よりも財産管理が可能になり、家庭裁判所への申し立ても必要ありません。
A.必ずしもそうとは限りません。認知症には軽度から重度まで様々な段階があり、「認知症の診断=意思能力がない」と直結するわけではなく、軽度の認知症であれば、遺産分割協議の内容を十分に理解し、判断できる意思能力があると認められる場合もあります。
後々、意思能力が争点になるトラブルが生じないように医師から「判断能力がある」旨の診断書を取得しておくことをおすすめします。
A.状況に応じて相談先が異なります。遺言書や家族信託、成年後見制度の場合は弁護士や司法書士、相続税申告や節税対策については相続税に強い税理士に相談しましょう。どの専門家に相談するか分からない場合であっても、まずは相続の専門家へ相談し、ご自身の状況に合ったアドバイスを受けることが重要です。
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議ができずに財産が凍結されるだけでなく、未分割での相続税申告で納税額が大幅に増加する大きなリスクが生じます。相続発生後には成年後見制度を利用する方法がありますが、費用や時間、財産管理上の制約も伴うため、相続発生前の元気なうちに「遺言書」や「家族信託」といった生前対策を講じておくことが重要です。
当事務所は、遺言書作成などの生前対策についてのご相談も承っております。将来の相続税申告について不安な場合は、まずは以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
