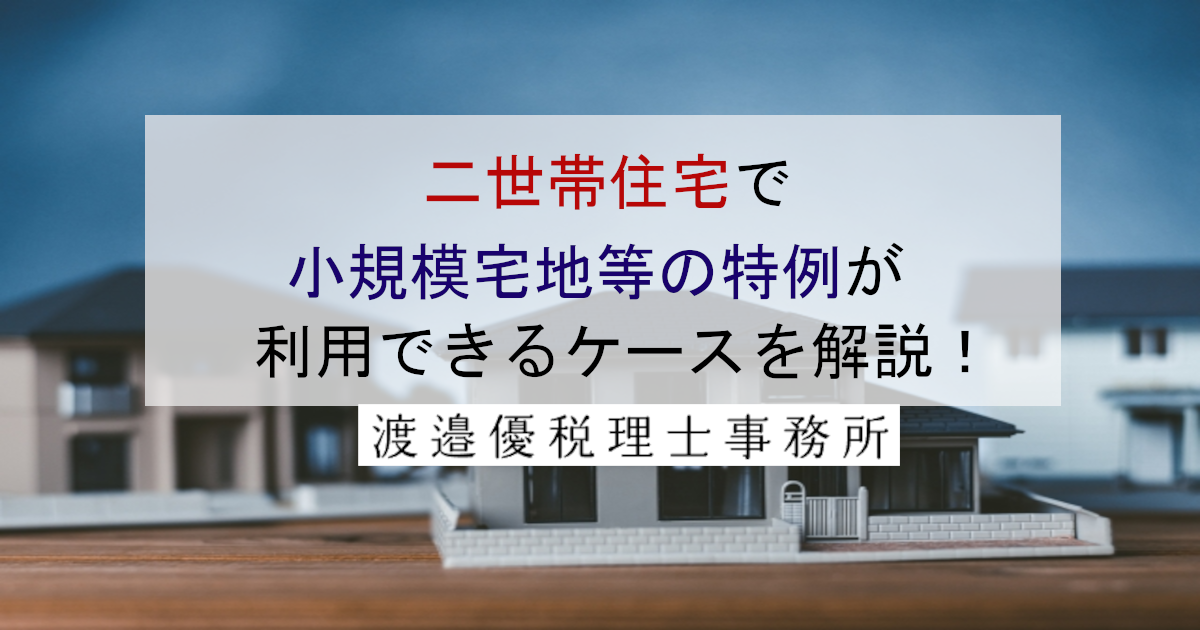
相続税の特例で最も注意しなければならないものが「小規模宅地等の特例」です。小規模宅地等の特例を適用できれば、宅地の相続税評価額を最大で80%減額することができ、相続税の負担を大きく減らすことが可能です。
しかし、小規模宅地等の特例の要件は複雑になっており、特に二世帯住宅で特例を適用するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。ここでは「二世帯住宅で小規模宅地等の特例が利用できるケース」について詳しくご紹介します。
目次
小規模宅地等の特例は、自宅の土地などが適用対象となり、一定の要件のもとで330㎡まで評価額を最大で80%減額することができるなどの特例です。例えば、自宅の土地が300㎡で、評価額が6,000万円であった場合、特例を適用すると4,800万円減額され、残りの1,200万円が相続税の対象になります。
特例の詳しい内容については「【土地の評価を最大で80%減額】小規模宅地等の特例をわかりやすく解説!」で解説していますので、ご参照ください。
小規模宅地等の特例は、二世帯住宅であっても利用することが可能ですが、建物の構造や不動産登記の状況によっては特例が利用できない場合もあります。二世帯住宅で特例を利用するための要件は次のとおりです。
・1棟の建物に居住している(区分所有登記なし)
・建物の敷地が被相続人名義である
・相続人が特例を受ける敷地の建物に無償で居住している
・相続人が申告期限まで現状のままその土地を保有し住み続ける
二世帯住宅で小規模宅地等の特例を利用するために重要なことは「区分所有登記がされていないこと」が重要です。区分所有登記とは、分譲マンションを想像してもらうとイメージしやすいと思いますが、同一の建物内で部屋別に登記を行うことを言います。
分譲マンションだけではなく、二世帯住宅であっても区分所有登記を行うことが可能です。二世帯住宅を建設する際に、区分所有登記にするのか、親または子の単独登記にするのか、親と子の共有登記にするのかを決めることができます。二世帯住宅の登記方法の特徴について見ていきましょう。
区分所有登記は、二世帯住宅を2戸の住宅とみなし、親と子がそれぞれの名義で建物の登記を行う方法です。どの二世帯住宅でも区分所有登記ができるのではなく、玄関がそれぞれ別に設けられていることなど、住宅のタイプが完全分離型でなければ区分所有登記にすることはできません。
区分所有登記を行うことで親と子の両方で住宅ローン控除を受けることができる税務上のメリットがあります。ただし、区分所有登記にしている場合は、敷地全体を小規模宅地等の特例の対象にすることはできません。
共有登記は、二世帯住宅を1戸の住宅とみなし、親と子が共有名義で登記を行う方法です。共有の割合については必ずしも50:50である必要はなく、基本的には住宅資金の出資割合によって決められます。
二世帯住宅を共有登記にすると、区分所有登記と同じく割合に応じて親と子の両方で住宅ローン控除を受けることができます。また、同居扱いとなるため、小規模宅地等の特例を適用することができます。
単独登記は、二世帯住宅を1戸として、親か子の単独名義で登記する方法です。単独登記には、建物内部で行き来が可能な非分離型と玄関が別々で建物内部で行き来が出来ない構造である完全分離型がありますが、どちらであっても小規模宅地等の特例を適用することができます。
二世帯住宅の敷地に小規模宅地等の特例が利用できるかについて、二世帯住宅のパターン別に見ていきましょう。
建物が親か子の単独登記で、建物内部で行き来が可能な非分離型である場合は、小規模宅地等の特例の利用が可能です。
建物が親か子の単独登記で、玄関が別々であり、建物内部で行き来ができない完全分離型である場合も、①同様に小規模宅地等の特例の利用が可能です。
以前は、単独登記であっても完全分離型になっている場合には特例の適用は認められていませんでしたが、構造の違いで相続税額が異なることは不公平であったため、2014年の改正により、完全分離型も特例の適用の対象として認められています。
単独登記と同様に、非分離型、完全分離型にかかわらず、小規模宅地等の特例を利用することができます。
区分所有登記の場合は、1つの建物に2戸の住宅があることになり、同居として認められず、小規模宅地等の特例を利用することはできません。
区分所有登記である場合、原則的に小規模宅地等の特例を利用することはできません。ただし、登記後の改修などにより建物内部で行き来ができるようになり、親と子の世帯の区別がなくなった場合については同居と認められ、小規模宅地等の特例の適用が認められる可能性があります。
例:玄関を1つにした場合、台所が1つで食卓と共にしている場合など
親が住む住宅(母屋)に子が生活できる住宅を増築した場合は、区分所有登記に該当せず、増築部分も含めて1つの建物になります。そのため、非分離型、完全分離型にかかわらず小規模宅地等の特例を利用することができます。
二世帯住宅が区分所有登記になっているかどうかについては、「固定資産税の納税通知書」で判別が可能です。区分所有登記になっている場合は、親と子それぞれ個別に固定資産税の納税通知書が届きます。また、1棟の建物でも家屋番号が2つあれば、区分所有登記になっている可能性が高いと言えます。
ここまで見てきたとおり、区分所有登記による二世帯住宅では小規模宅地等の特例を利用することはできません。既に区分所有登記がなされている二世帯住宅で小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、1つの建物に変更する「合併登記」が必要になります。
合併登記とは、2戸の住宅を1戸にまとめる「表題部の変更登記」のことを言います。合併登記を行うためには、各建物の所有権の登記名義人の住所・氏名・持分が全て同じであること、抵当権の設定がされていないこと等、いくつかの要件があります。
親か子の所有権を片方に贈与、または売却し、二世帯住宅を単独所有にすることで合併登記を行うことができます。ただし、譲渡する場合には売却益部分に所得税、贈与する場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。
二世帯住宅の場合「区分所有登記かどうか」で小規模宅地等の特例の適用が決まってきます。小規模宅地等の特例は、相続税額を大幅に節税できる可能性がある特例になりますので、生前から特例が利用できる状態に整えておくことが重要です。
もし、二世帯住宅が区分所有登記になっている場合は、合併登記ができないかどうかを検討し、早めに準備を行いましょう。
渡邉優税理士事務所は「不動産に強い税理士事務所」です。小規模宅地等の特例が利用できるようにする「合併登記」についても、土地家屋調査士と連携し、お手伝いさせていただきます。お悩みの際は、ぜひ下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
