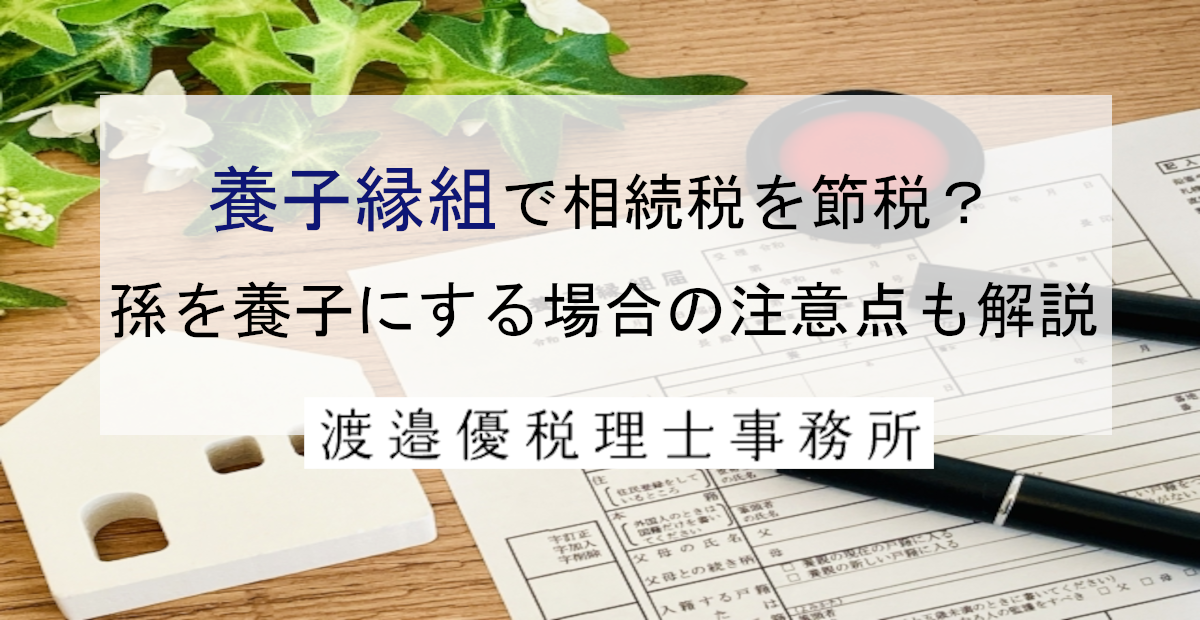
相続税では、法定相続人が増えると基礎控除が増加し、節税効果を期待することができます。そのため、相続税対策として養子縁組を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
養子縁組は相続税対策としてのメリットが多い制度ですが、注意しなければ相続税申告での養子が認められないおそれもあります。ここでは「相続税対策としての養子縁組のメリットや注意点」について、孫を養子にする場合の注意点も含めて解説します。
目次
養子縁組は、子どもがいない夫婦が養子を迎える場合や再婚相手の連れ子を養子にする場合などを思い浮かべると思いますが、相続税対策として行う養子縁組は主に「子どもの配偶者と養子縁組を行うケース」と「孫と養子縁組を行うケース」が一般的です。
子どもの配偶者と養子縁組を行うケースとは、長男の妻や長女の夫と養子縁組する場合です。「親切に介護してくれたから財産を残したい」という思いで長男の妻と養子縁組するケースや家業を継承するために長女の夫が婿養子になるケースなどが該当します。
孫と養子縁組を行うケースは「孫に家業を継がせる目的で養子縁組を行う場合」などが該当します。相続税対策のためだけに養子縁組をした場合は、税務上否認されるリスクがありますので注意が必要です。
相続税の計算では、法定相続人の数が増えることにより控除額や非課税限度額が増加するものがあるため、養子縁組を行うことにより相続税対策になります。
【相続人の数により節税になる要素】
①相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×相続人の数
②生命保険金の非課税限度額:500万円×相続人の数
③死亡退職金の非課税限度額:500万円×相続人の数
※上記の相続人の数に含めることができる養子には制限があります。
・実子がいる場合:養子は1人まで
・実子がいない場合:養子は2人まで
【普通養子縁組と特別養子縁組の違い】
養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組があり、上記の養子縁組の制限は普通養子縁組の場合に適用されます。普通養子縁組は、実の親との血縁関係は残るため、実親と養親の両方の相続権を持つのに比べ、特別養子縁組は実親との血縁関係が解消され養親の相続権のみを持つことになります。
また、相続税の課税方式は累進課税であるため、ケースによっては養子縁組により相続人が増えることで相続税率が下がることもあります。
孫と養子縁組すれば、孫は相続人となり、遺言書がなくても孫に財産を相続させることができます。ただし、孫が財産を相続する場合の相続税は2割加算になるので注意が必要です。
養子縁組により相続人の数が増えることで相続税の節税対策になりますが、注意しなければならないポイントもあります。
養子縁組により相続人になった場合、他の相続人と同等の相続権を得ることになります。そのため、実子の相続分の割合が減ってしまうことになり、遺産分割協議でもめてしまう可能性があります。
例えば、実子が3人いる相続で実子のうちの1人の配偶者と養子縁組した場合、もともとは3分の1の相続分あったはずが4分の1になってしまうため、遺産分割協議でなかなか合意に至らなかったり、兄弟姉妹の関係性が悪くなってしまったりするリスクがあります。
養子縁組による遺産分割トラブルを避けるためには、養子縁組する前に家族の意向をしっかりと確認し、他の相続人に配慮した遺言書を作成するなどの対策が必要になります。
養子縁組を行うと相続税対策になることは事実ですが、相続税対策だけを目的とした養子縁組であると税務署に判断されてしまった場合「相続税を不当に減額させる行為」として、養子縁組による基礎控除や非課税限度枠の増加が認められません。
相続税法第63条の2
被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるものを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。
「孫を跡取りにするため」「長い間介護をしてくれた長男の妻に財産を相続させたい」など、正当な理由があるものは問題ありませんが、節税目的のために「亡くなる直前に養子縁組した場合」や「養子縁組した人が理由なく相続放棄した場合」など、明らかに節税だけを目的とした養子縁組である場合は税務署に否認される可能性が高くなります。
孫と養子縁組を行うと、本来であれば親から子へ、子から孫へと相続される財産が親から孫へ直接相続することになり、相続税の課税のフィルターを一代飛ばすことになります。孫を養子にした家族と比べると税負担の不公平が生じてしまうため、養子になった孫が財産を相続した場合には、相続税の2割が加算されます。
二重相続資格者とは、1人で2人分の相続資格がある人のことを言います。孫養子を行っている場合で実親(祖父の子)が既に亡くなっており、その後に養親(祖父母)が亡くなった場合、孫は「養子としての相続人の地位」と「実親の代襲相続人としての相続人の地位」があることになります。
※代襲相続とは、相続が生じたときに本来は相続人となる人が既になくなっている場合に亡くなっている相続人の代わりに次の相続人が相続する制度のことを言います。
二重相続資格者になると、「2人分」の相続分が認められます。ただし、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税限度枠の計算などのカウントでは「1人」になるため、間違えないように注意しましょう。
養親よりも先に養子が亡くなり、養親がその後に亡くなった場合には、養子の子が代襲相続人として相続権を持つことになります。ただし、養子の子が生まれたときに既に養子縁組を行っているかどうかで代襲相続人になれるのかを判断することになります。
・養子の子が養子縁組前に生まれていた場合:代襲相続しない
・養子の子が養子縁組後に生まれていた場合:代襲相続する
相続発生時点で養子である孫が未成年者である場合は、未成年者の代わりに遺産分割協議や各種相続手続きを行う「特別代理人の選任手続き」が必要です。特別代理人の選任手続きは、家庭裁判所へ申立てを行わなければならず、手続き完了までに数か月を要することがあります。
養子縁組は、相続税の観点からは相続税を抑える効果があります。ただし、養子縁組を行うことで他の相続人との軋轢を生んでしまい、相続トラブルに発展してしまうおそれもあるため、養子縁組を行う場合には慎重な検討が必要です。
また、孫養子を行う場合には、さらに複雑になり、2割加算により相続税の負担が重くなってしまう可能性もあるため、安易に実行するのではなく、生前贈与など、他の方法も検討することをおすすめします。
当事務所では、生前からの相続税対策についてのご相談も承っております。お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
