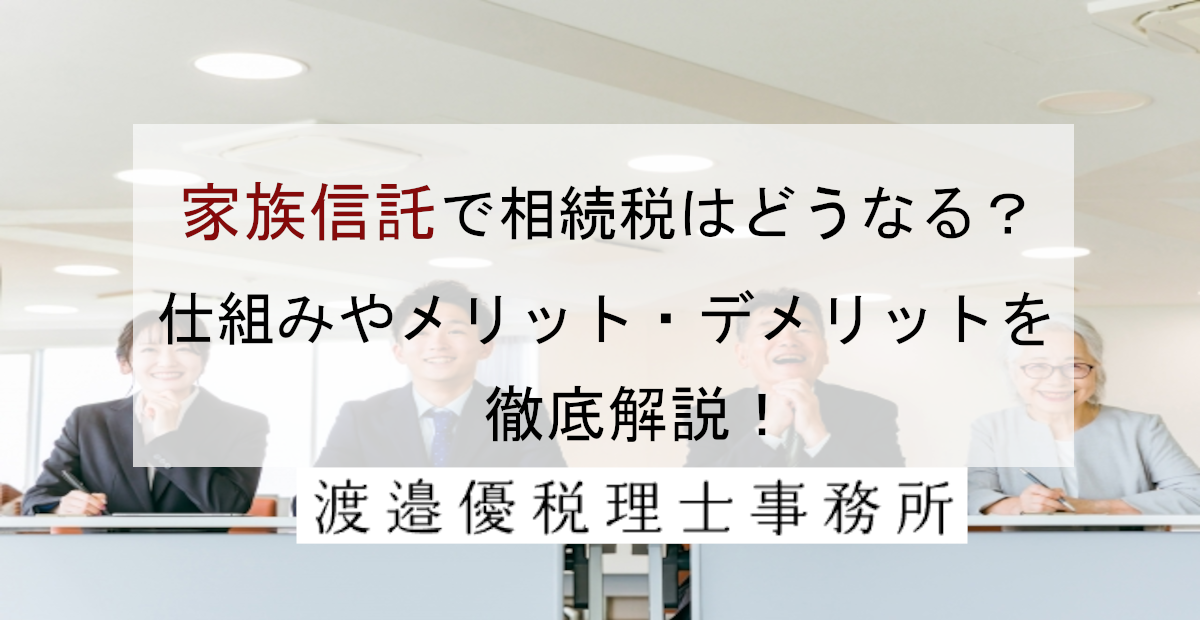
将来の相続を考えると「老後の財産管理が不安…」「認知症になったら資産が凍結されるかもしれない」「自分が亡くなった後、家族に円満に資産を引き継がせたい」と悩みを抱える方の間で、今「家族信託」という制度が注目されています。
家族信託を活用することで元気なうちから信頼できる家族に財産の管理を託すことができ、将来の認知症による資産凍結を回避したり、スムーズな資産承継を実現したりすることが可能になります。
しかし、家族信託を検討する場合に注意しなければならないものは相続税との関係性です。ここでは「家族信託と相続税の関係について、仕組みやメリット・デメリット」を解説します。
家族信託とは、自分の不動産、預貯金などの財産の管理や処分を、信頼できる家族に託すための法的な契約のことを言います。認知症などで自身の判断能力が低下した場合に備え、財産管理をスムーズに行うことを主な目的としている制度です。
家族信託の仕組みを理解するためには、鍵となる3人の登場人物の役割を押さえておきましょう。
【家族信託の登場人物】
• 委託者:財産を預ける人。もともとの財産の所有者です。
• 受託者:財産を預かり、管理・運用・処分する人。信頼できる家族が担います。
• 受益者:信託された財産から生じる利益(家賃収入や売却代金など)を受け取る人です。委託者と受益者は同一でも構いません。
【家族信託の例(自益信託)】
日本の家族信託では、多くの場合で委託者と受益者が同一人物であり、財産を預ける親自身が利益を受け取る「自益信託」という形式で行われます。自益信託であれば、財産の名義が父から子に移っても実質的な所有者は父のままとみなされるため、贈与税の負担は生じません。
自益信託を活用することで、例えば父(委託者)が認知症になったとしても、子(受託者)が父の介護費用や生活費のために預金を引き出したり、不動産を売却したりすることが可能になります。
家族信託の活用は、認知症のリスクを回避やスムーズな資産継承が可能になり、相続対策として非常に効果的です。では、家族信託は相続税対策として効果的でしょうか。
結論から言うと、家族信託という制度自体に直接的な相続税の節税効果はほとんどありません。
家族信託を活用しても信託財産の実質的な所有者は受益者(多くの場合は親)のままです。そのため、受益者が亡くなった場合、その信託財産(正確には「受益権」という権利)は通常の財産と同様に相続税の課税対象となり、財産を信託したからといって、その評価額が下がるわけではなく、相続税を直接的に節税する効果はありません。
家族信託には直接的な相続税の節税効果はありませんが、「間接的な相続税対策」として効果を期待することが可能です。
なぜなら、認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売買や建築、贈与といった法律行為ができなくなり、相続税対策が一切できなくなってしまうのに対し、家族信託を活用すれば、本人の判断能力が低下した後でも、受託者(子など)が本人のために、計画していた相続税対策を継続して実行できるからです。
具体的には、以下のような家族信託を利用した相続税対策が考えられます。
被相続人が認知症になった場合、不動産などの売却ができず、将来発生する相続税の納税資金の捻出ができずに困ってしまうケースも珍しくありません。家族信託を利用することで、親が認知症になった後でも、子が信託された収益性の低い不動産を売却し、納税資金を確保したり、より収益性の高い不動産に組み換えたりすることが可能です。
相続税対策では、財産の相続税評価額を引き下げることが非常に重要であり、不動産を購入することで評価額を圧縮することができます。不動産の相続税評価額は実勢価格(市場価格)よりも低く設定されており、現金を不動産に「組み替える」ことで相続税を引き下げることが可能です。
例えば、更地の土地に賃貸マンションを建設すると、その土地や建物の相続税評価額を引き下げる効果が期待できます。しかし、マンション建設には時間がかかります。もし建設中に親が認知症になってしまっても、家族信託を組んでいれば、子が契約を引き継ぎ、計画を中断することなく進めることが可能です。
信託契約では、受託者に報酬を支払う設定を行うことが可能です。報酬として親の財産を計画的に子に移転させることで結果的に相続財産を減らす効果も期待できます。
家族信託は「節税そのもの」ではなく、節税対策を実行し続けられる状態を維持するという点で、非常に大きな効果があります。
受益者(親)が亡くなった場合、信託財産(受益権)は相続税の対象になります。どのように課税されるかは、信託契約の内容によって大きく2つに分類されます。
多くの信託契約では「当初の受益者(親)の死亡」をもって信託を終了させると定めており、この場合は契約によって定められた「帰属権利者」が信託財産を承継します。そのため、相続税の納税義務者は帰属権利者になります。
家族信託では、受益者の死亡後も信託契約を終了させず、次の受益者を指定(受益者連続信託)をしておくことも可能です。例えば、「最初の受益者は父、父の死亡後は母を第二受益者とする」という契約にすることもできます。
この場合、最初の受益者(父)が亡くなると、契約に基づき、次の受益者(母)が受益権を引き継ぎます。このとき、新たに受益者となった母が遺贈によって財産を取得したとみなされ、相続税が課税されることになります。
税金という観点から、家族信託のメリットとデメリットを整理してみましょう。
委託者=受益者である自益信託の場合、信託を開始しても実質的な財産の移転はないとみなされるため、高額になりがちな贈与税や不動産取得税の負担なしに名義を受託者に移すことができます。ただし、信託契約終了時に不動産取得税が発生します。
信託した不動産から生じた所得(家賃収入など)が赤字になった場合、その信託財産以外からの所得と相殺することはできず、赤字がなかったものとして取り扱われます。これは「信託の損益通算禁止」という税務上のルールで、不動産賃貸を行っている場合は特に注意が必要です。
家族信託を活用する際には、次の点に注意しましょう。
家族信託は、遺言と同様に財産の承継先を指定する機能を持っています。そのため、一部の相続人に偏った信託の設計を行うと、他の相続人の「遺留分(最低限の相続権)」を侵害してしまう可能性があります。他の相続人への遺留分に配慮した信託設計を行うようにしましょう。
受託者は、財産の管理という大きな責任を負うことになります。また、信託の当事者以外の家族から不公平感を抱かれ、トラブルに発展する可能性も考えられます。トラブルを回避するには「なぜ家族信託を行うのか」その目的や内容について、家族全員で十分に話し合い、理解を得ることが大切です。
A.現金、不動産、非上場株式などの財産については制限がありません。一方で、農地や年金受給権など、法律で譲渡が制限されている財産は信託できません。
A.家族が受託者になる場合は、契約で定めれば報酬を支払うことは可能ですが、必ずしも必要ではありません。
A.法律上、自分で行うことは可能ですが、契約内容の設計や契約書の作成は非常に専門的で複雑です。後々、トラブルにならないように法務・税務の知識を持った弁護士や税理士に相談しましょう。
家族信託は、認知症による資産凍結などの大きな課題に対応できる制度ですが、信託設計には法務や税務の知識が必要不可欠です。ご自身や家族にとって最適な形を実現するためにも、まずは相続税や家族信託に精通した税理士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所は、家族信託を活用した相続対策についてのご相談も承っております。相続対策をご検討の際は、以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
