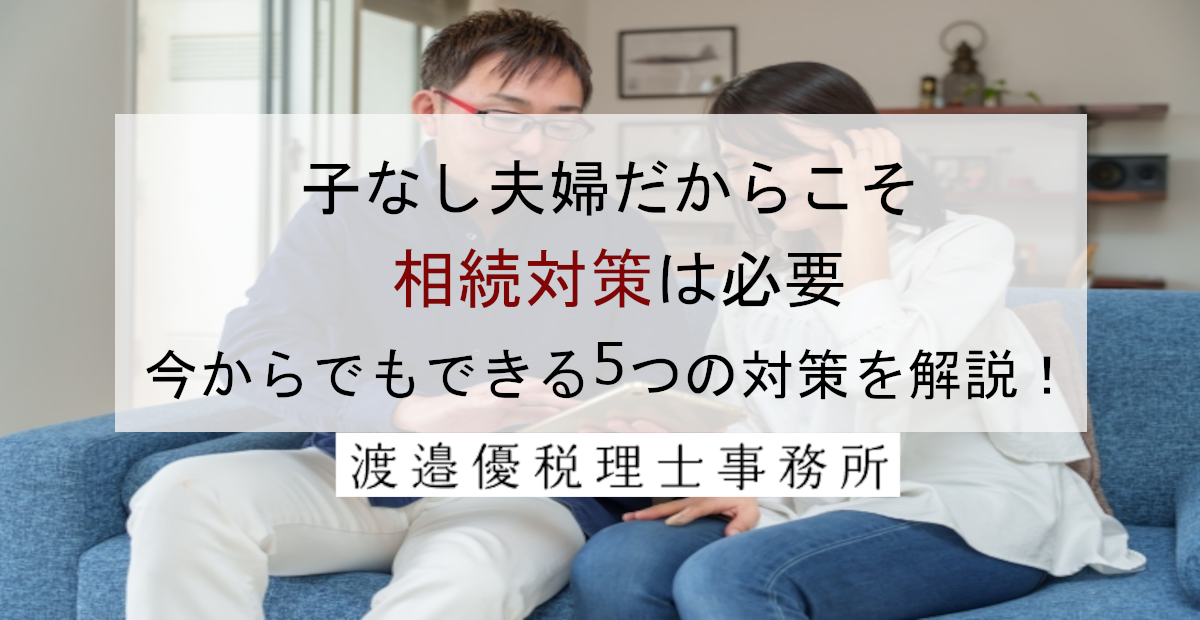
「結婚=子どもを持つ」ということに対する価値観の変化や夫婦ふたりの生活を楽しみたいなど、現代では子なし夫婦の割合は増加傾向にあります。子どもがいない夫婦の場合、相続について考える機会はあまり多くないかもしれませんが、子どもがいないからこそ相続対策は不可欠です。
「夫婦のどちらかが亡くなったら、配偶者が全て相続するから問題ないのではないか」と思っている方もいるかもしれませんが、配偶者以外の親族が相続人になる場合もあり、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
ここでは「子なし夫婦だからこそ必要な相続対策」について詳しく解説します。
目次
相続では、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。子なし夫婦の場合も同様に夫婦のどちらかが亡くなった場合には配偶者が必ず相続人になりますが、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
相続人には優先順位があり、第1順位:子、第2順位:直系尊属(両親、祖父母等)、第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子どもである姪や甥)になります。
子なし夫婦の場合は、第1順位の子がいないため、第2順位または第3順位が相続人になります。
【子なし夫婦の相続人のパターン】
・配偶者のみが相続人になる場合⇒相続割合は全て配偶者
亡くなった被相続人に両親(祖父母)がおらず、兄弟姉妹・甥姪がいない場合が該当
・配偶者と両親(祖父母)が相続人になる場合⇒相続割合は配偶者が2/3、両親(祖父母)が1/3
亡くなった被相続人に両親(祖父母)がいる場合が該当
・配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合⇒相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹(甥姪)が1/4
亡くなった被相続人に両親(祖父母)がおらず、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)がいる場合が該当
子なし夫婦の相続では、亡くなった被相続人の両親や兄弟姉妹、甥姪が相続人になる可能性があり、子どもがいる夫婦の相続よりも関係性が離れているため相続トラブルが生じやすくなります。
子なし夫婦の相続で発生する主なトラブルには次のようなものがあります。
遺言書がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するのかを話し合う「遺産分割協議」が必要になります。子なし夫婦の場合で配偶者以外に相続人がいる場合は、亡くなった被相続人の両親または兄弟姉妹(甥姪)と遺産分割について話し合わなければなりません。
遺産分割協議は、財産に関わるものであるため、実の親子であっても話しにくい内容です。その話を義理の両親や兄弟姉妹(甥姪)と行わなければならない状況は配偶者にとって大きな負担になるでしょう。
場合によっては、義理の両親や兄弟姉妹(甥姪)との話がいつまでもまとまらず、相続手続きが進まないという状況に陥ってしまうこともあります。
相続財産の中でも不動産は遺産分割が難しい財産です。亡くなった被相続人が自宅などの不動産を所有していた場合には、その不動産を誰が相続するかでトラブルになってしまう可能性があります。
例えば、亡くなった被相続人が自宅の所有者である場合で自宅以外の財産をあまり保有していない場合、配偶者が自宅を1人で相続するために他の相続人へ代償金を支払わなくてはならない状況になってしまう場合もあります。
最悪の場合、代償金が払えずに自宅を売却しなければならない状況に陥ってしまう可能性も考えられます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合は、相続人の数が多くなってしまうことがあります。特に、兄弟姉妹の誰かが亡くなっており、その人の子(甥姪)が相続人になる場合には相続人の数が増えやすく、遺産分割協議の連絡などに時間と手間がかかる可能性があります。
子なし夫婦の場合は、残された配偶者が相続で苦労しないためにも生前から対策を行うことが重要です。今からでもできる子なし夫婦に有効な5つの相続対策を見ていきましょう。
遺言書で相続財産の分け方の指定がある場合は、遺言書が遺産分割協議よりも優先されます。そのため、配偶者に相続させる財産を指定した遺言書を作成することで、他の相続人と遺産分割に関する話し合いを行わずに相続手続きを行うことができ、相続トラブルを回避することが可能です。
遺言書により、配偶者に特定の財産を相続させることもできますし、全ての財産を配偶者に相続させることもできます。
ただし、遺言書であっても相続人の遺留分を侵害することはできません。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、被相続人の両親(祖父母)が相続人になる場合には1/6の遺留分があります。遺言書で「配偶者に全ての財産を相続させる」とした場合であっても、相続人である両親は遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分でトラブルが生じそうな場合には、遺留分にも配慮した遺言書を作成しましょう。
生命保険に加入し、配偶者を受取人にしておくと被保険者が亡くなったときに受取人に保険金が支払われます。この保険金は契約に基づいて受取人が受け取る権利を持つ固有の財産として取り扱われるため、相続財産には含まれず、遺留分の対象にもなりません。保険金をめぐってトラブルになることはないため、相続対策として有効です。
また、相続税の計算では「みなし相続財産」となり課税対象になりますが、非課税枠が設定されているため生命保険の活用は相続税対策としても効果的です。
生命保険の活用については「相続税対策には生命保険の活用が第一|でも、契約内容には注意が必要」をご覧ください。
生前に配偶者へ生前贈与を行い、自宅を移転させておく方法も相続対策として効果的です。本来、夫婦の間で行った生前贈与は、遺産の前渡し扱い(特別受益)を受けることになり、相続財産に加算して遺産分割が行われることになります。
しかし「婚姻期間が20年以上の夫婦間において自宅の贈与を行った場合には、遺産の前渡し扱いをしなくてよい」という民法の改正が2019年に行われたため、自宅については他の相続人の影響を受けることはありません。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合に2,000万円まで贈与税の対象から控除される制度を利用することも可能です。
家族信託では、遺言書と同じ様に財産の継承先を指定することができます。さらに「配偶者が亡くなった後に誰にその財産を相続させるのか」までを指定することが可能です。
「夫婦二人とも亡くなった後はお世話になった人や関係性の深い人に自分たちの財産を相続させたい」という希望がある場合には、家族信託を活用することで実現させることができます。
不動産が相続財産にある場合の遺産分割は分け方や処分に苦労してしまうことが多いため、できるだけ配偶者に負担をかけないようにするためには、不要な不動産は現金化しておくといいでしょう。現金化することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができるようになります。
A.子なし夫婦の相続人は配偶者だけだとは限りません。被相続人の両親(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)がいる場合には、配偶者と両親(祖父母)、配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になります。
A.配偶者以外の相続人がいる場合、配偶者とその相続人との間での遺産分割協議でトラブルになる場合があります。トラブルになってしまうと相続手続きを進められなくなり、関係性も悪化してしまうため、生前からの対策が重要です。
A.子なし夫婦の相続対策には「遺言書を作成する方法」や「配偶者を生命保険の受取人にする方法」「配偶者に自宅を生前贈与する方法」「家族信託を活用する方法」「不要な不動産を現金化する方法」などがあります。
子なし夫婦の一方が亡くなった場合、何も対策していなければ残された配偶者がトラブルに巻き込まれ、苦労してしまうおそれがあります。配偶者が相続で苦労しないためにも、遺言書の作成などを行い、もしもの時に備えておきましょう。
当事務所では、子なし夫婦の相続対策についてのご相談も承っております。お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
