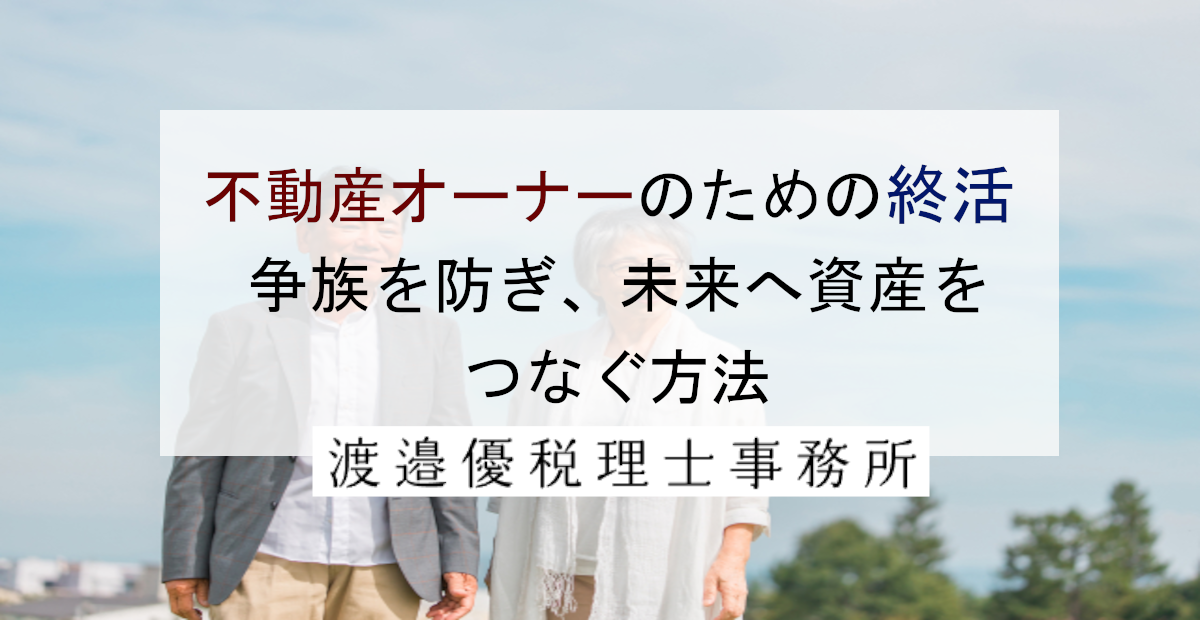
「終活」とは、元気なうちに人生の最期について考え、様々な準備を行うことであり、財産のリストアップや整理、遺言書の作成、葬儀やお墓の準備などが挙げられます。
終活を行う最大の目的は「自分の死後に家族が困らないようにすること(家族に迷惑をかけたくない)」という方が多く、終活は人生のより良い最期を迎えるための準備とも言えます。
もし、終活をせずに亡くなってしまうと、自分の意思表示がないまま相続が発生し、遺族は葬儀や相続、遺品整理などで想像以上に困ってしまいます。特に、不動産オーナーの場合、終活をしていなければ大きなトラブルに発展するリスクが非常に高いため、相続トラブルを回避するために早めの準備が必要です。
ここでは「不動産オーナーの終活」に焦点を当てて、具体的な整理方法や税務上の考慮点を含めて詳しく解説します。
目次
不動産を所有している場合、資産性があるという「長所」がある一方で、相続においては「短所」と「リスク」が考えられます。
不動産相続の長所は、現金と比べて相続税評価額が下がる点にあります。相続税の計算では、不動産は現金や預貯金よりも低い評価額になりやすく、相続税の対象となる評価額を抑えることが可能です。
そのため、現金や預貯金などの流動資産を不動産に組み替えることは、相続税評価を下げ、節税対策として非常に有効な手段となります。賃貸用不動産の建設であれば、さらに評価額が下がる効果が期待できます。
詳しくは「【不動産で相続税を節税できる】不動産を使った節税方法を解説!」をご覧ください。
不動産相続の短所は、相続税を納付するための資金が不足してしまう傾向が強いことです。相続税は10か月という申告期限があり、相続税の納付も同時に行わなければなりません。不動産はすぐに現金化することが難しい資産であるため、不動産を相続した相続人は自己資金で相続税の納税資金を準備しなければなりません。
納税資金が足りなければ、相続した不動産を処分しなければならない状況になってしまうおそれがあるため、不動産オーナーの相続では「納税資金対策」が非常に重要です。
代々引き継いだ不動産は単なる資産ではなく、家族の歴史や思い出が詰まった大切な財産です。代々の不動産を相続した場合、他の相続財産と比べて思い入れが強くなるため、客観的に最善の判断がしづらくなるという短所が考えられます。
例えば、相続した不動産の価値が下がると分かりながら処分できずに保有し続け、最終的に低価格で売却することになってしまうケースなどが該当します。
終活では、所有不動産の優劣や将来手放す際の出口戦略など、一歩下がった「ドライな目」で見渡すことが大切です。
終活において、所有する不動産をどう扱うかについては、大きく「手放す」「活用する」「残す」の3つの選択肢があります。どの選択肢を選ぶべきかについては、老後資金の見通しや今後のライフプラン、家族の意向、そして所有する不動産の立地や価値によって異なるため、慎重に検討しましょう。
使わなくなった不動産や利用予定のない土地などは、生前に手放す(整理する)ことで、老後の資金確保や将来の相続トラブル回避に繋がります。
将来的に使用する予定のない不動産で家族が全員処分することに同意しているのであれば、不動産を売却して現金化することをおすすめします。
不動産を売却し、まとまった資金を得ることで、老後の生活資金や老人ホームなどの施設入居費用に充てることができます。また、不動産を現金化することで相続発生時の遺産分割トラブルを回避することが可能です。
生前に子どもや孫など、特定の相続人に不動産を引き継がせたい場合は「生前贈与」を検討してもいいでしょう。不動産の生前贈与は、所有者自身が相手を選び、確実に不動産の引き継ぎを見届けることができ、亡くなった後に遺産分割で揉める心配がなくなります。
ただし、不動産の贈与では贈与税が課税されます。贈与税は相続税よりも税率が高くなりやすく、税負担が増加する可能性があるため注意が必要です。また、相続開始前10年以内の生前贈与は遺留分の計算の対象になるため、慎重に検討しましょう。
不動産を手放したくないが、老後資金や介護資金のため不動産を活用したい場合は「不動産の賃貸」を考えてみましょう。
空き家になった家屋を賃貸に出す、あるいは空き地にアパートを建てたり、月極駐車場として利用したりすることで、定期的な収入を得ることができます。また、空き家を賃貸に出すことで相続税評価額を下げることができ、相続税対策としても有効です。事業性が認められれば相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」の対象になる可能性もあります。
ただし、賃貸経営にはリフォームや建設費などの初期費用、空室リスク、修繕費、管理の手間などの負担があるため、長期的な収支計画を立てて判断する必要があります。
家族の思い出が詰まった自宅や先祖代々の土地を大切に残したいという場合には、遺言書の作成や家族信託の活用、円滑な承継のための対策を必ず行うようにしましょう。
不動産は物理的に均等に分割することができないため、相続時にトラブルになりやすい財産です。誰に何を相続させるか明確に意思を記しておくためにも、遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を経ずに手続きを進められることが多く、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。もし、相続人の1人が認知症などで意思表示ができない状態に陥っていても手続きを進めることが可能です。
不動産オーナーが認知症などで判断能力を失うと不動産を処分することも、活用することもできません。このような状況を回避するためには、家族に財産管理と承継を指定する「家族信託」が有効です。
家族信託については「「家族信託」で相続税はどうなる?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説!」をご覧ください。
終活を成功に導くためには、行動を起こすことが重要です。「始めよう」と考えていても行動に移さなければ意味がありません。まずは次の順番で進めてみましょう。
不動産の整理方法を決める前に大切なのは「将来的にどのように過ごしたいのか」という今後のライフプランを思い描くことです。どこに住み続けたいのか、介護が必要になった場合の対応など、今後のライフプランをできるだけ明確にし、年金収入や貯蓄だけで老後資金が足りるかどうかの見通しを立ててみましょう。
相続財産の種類が多いほど、相続時の手続きは煩雑になり、残された家族の負担が増加します。家族の負担を少しでも軽減できるように全ての財産をできるだけ正確に洗い出し「財産目録」を作成することが最初のステップとして非常に大切です。
財産目録には、所有する全ての財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険など)と負債(ローンや保証債務など)を記載しましょう。
終活を成功させるには、家族とのコミュニケーションが最も重要です。親がよかれと思って決めたことが後からトラブルの原因になる可能性があるため、自分一人で決めずに必ず家族の意向を聞くことようにしましょう。
特に不動産の売却、活用、相続といった整理方法を決める前には、家族の意見を聞き、腹を割って話すことが将来的なトラブルの回避に繋がります。
終活や生前対策は「オーダーメイドの対策」が必要になります。自分では「問題ない」と思っていることであっても、将来的に争いの種になってしまったり、相続税の負担が重くなってしまったりすることもありますので、後悔しないためにも専門家への相談が大切です。
特に、税理士の役割は相続税対策の「要」になります。現状の財産の把握から相続税の試算、節税対策の立案など、相続税に強い税理士は終活において大切な部分をサポートすることが可能です。
A: 不動産は現金や預貯金のようにわかりやすく均等に分割できないため、相続が発生した後に遺産分割を巡って相続人同士のトラブル(争族)の元になりやすい資産です。遺言書を作成しておけば、ご自身の意思に従った分割が可能となり、相続発生後の手続きをスムーズに進められる可能性が高くなります。
A: 相続税を大幅に軽減できる特例の「小規模宅地等の特例」は、不動産オーナー様にとって最も強力な節税策の1つです。ただし、この特例は適用要件が複雑なため、終活で検討する際には注意が必要です。
終活は、人生の最期に向けて前向きに生きるための取り組みであり「終わり」ではなく「始まり」です。終活を行う目的は「家族に迷惑をかけないこと」「病気や介護に備えること」そして「老後を充実させること」です。
特に不動産の整理は、その性質上、遺産分割の難しさや納税資金不足といったトラブルの原因になりやすいため、早めに着手し、家族と話し合うことが大切です。
当事務所は、不動産オーナーの終活に関するお悩みについても対応しております。生前からのご相談については、以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
