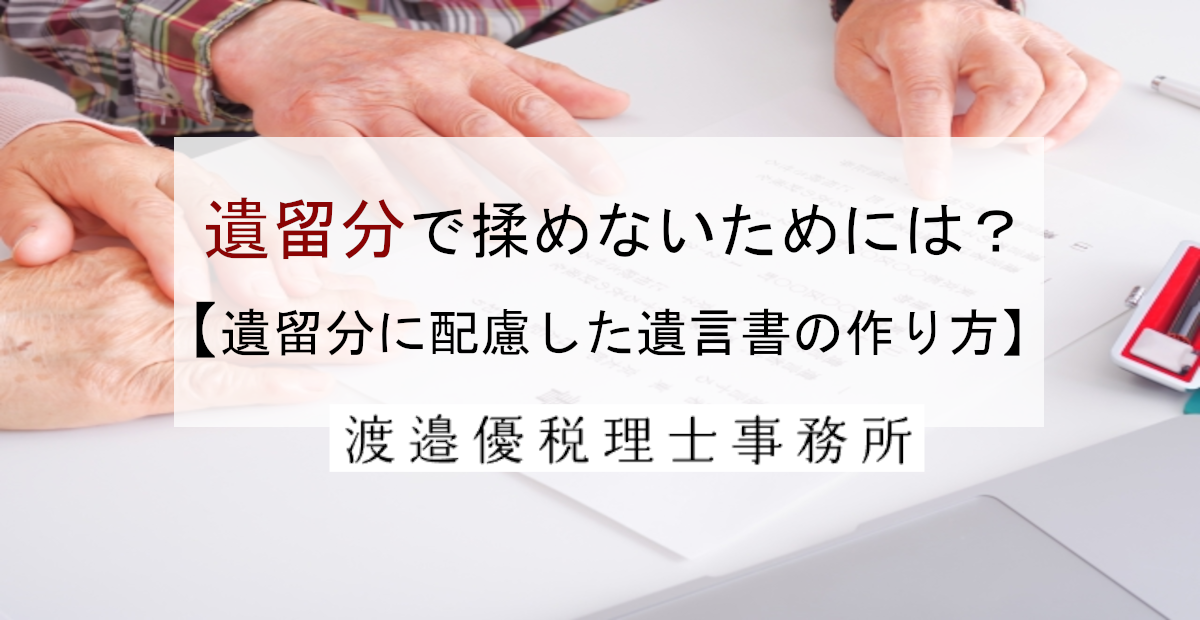
相続では、法定相続人(兄弟姉妹以外)が最低限相続できると保証されている割合である「遺留分」が存在します。遺留分を無視し、一部の相続人の遺留分を侵害した遺産相続を行うと相続トラブルに発展し、遺留分侵害額請求が行われ争いが長期化するなどの不利益が生じてしまいます。
将来発生する相続で遺留分トラブルを回避するためには「遺留分に配慮した遺言書の作成」が効果的です。ここでは「遺留分に配慮した遺言書の作り方」について詳しく解説します。
目次
遺留分とは、民法で定められた法定相続人(兄弟姉妹以外)の権利のことを言います。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
上記の条文をわかりやすく表にすると次のとおりです。
【各相続人の遺留分の割合】
相続人が最低限もらえる遺産(遺留分)を侵害された場合は、遺留分を取り戻すことが可能です。(遺留分侵害額請求)
ただし、遺留分侵害額請求は権利であって、侵害されたからといって必ずしも権利を行使しなければならないわけではありません。遺留分侵害額請求を行使するかどうかは権利者次第です。
相続では、遺言書がある場合は、原則的に遺言の内容が遺産分割協議や法定相続分よりも優先されることになります。しかし、遺留分は遺言の内容に関係なく相続人が最低限の相続財産を請求できる権利であるため、遺留分を侵害する遺言書を作成してしまうと相続で遺留分が問題になってしまうおそれがあります。
法的には遺留分を侵害する遺言書を作成しても問題なく、無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害する遺言書を作成することによって相続トラブルを引き起こしてしまう可能性があるため、遺留分に配慮した遺言書の作成が重要となります。
複数の相続人がいるのにも関わらず、そのうちの1人だけに全てを相続させる遺言は遺留分を侵害する遺言であり、何も相続できなかった相続人が不満を感じて遺留分侵害額請求を行うことがあります。
【よくある遺留分を侵害してしまうパターン】
・長男に全ての財産を相続させる遺言
・相続人に遺産を一切相続させず、第三者に全ての財産を遺贈する遺言
・ひとまず配偶者に全て財産を相続させる遺言
遺留分を侵害する遺言を作成すると、自分が亡くなった後に相続人同士でトラブルになるリスクが高まります。多くの相続人は、財産を相続できると期待しているものです。もし、特定の人だけが財産を相続し、自分は何も相続できなかった場合は、財産を相続した人に対して、不公平感、不満、失望、悲しみ、怒りなどの負の感情を抱いてしまい、ケースによっては憎しみに変わることもあります。
残された相続人のために作成した遺言書がきっかけで、家族の絆を壊してしまうことはとても悲しいことではないでしょうか。そうならないためにも、遺留分で揉めない遺言について検討してみましょう。
遺言がきっかけで揉めないためには「遺留分対策」をしっかりと行う必要があります。ここからは「遺留分侵害額請求されない遺言書の作り方」について解説します。
遺留分の割合は、相続人との関係性によって変わります。相続人ごとに「どのくらいの財産を相続させれば遺留分を侵害しないか」を把握しなければ、対策を行うことができません。
まずは、冒頭で紹介した「各相続人の遺留分の割合」を参考に各相続人の遺留分の割合を把握しましょう。
具体的な遺留分の額は「遺留分の基礎となる財産×遺留分の割合」で求めることができます。遺留分の基礎となる財産は、遺産総額に生前贈与した財産や遺留分を侵害することを予期して被相続人が売却した財産を加算し、被相続人に債務がある場合には控除します。
【遺留分の計算例】
相続人:子3人(長男、長女、次女)
遺産総額:1億円
相続開始前の1年間にした生前贈与:3,000万円
債務:1,000万円
・遺留分の基礎となる財産:1億円 + 3,000万円 - 1,000万円 = 1億2,000万円
・子の遺留分の総額:1億2,000万円 × 遺留分割合1/2 = 6,000万円
・子1人の遺留分:6,000万円 × 相続分割合1/3 = 2,000万円
遺留分を把握したら、できるだけ遺留分に配慮した内容の遺言書を作成しましょう。そうすることでトラブルを回避することができます。どうしても一部の相続人の遺留分を侵害してしまう場合は、遺言書の「付言事項」を活用して想いを伝えましょう。
付言事項とは、遺言書の中で相続人への想いを記載する条項です。「なぜこのような遺言書を残したのか」「相続人同士で争わないでほしいこと」「各相続人への想い」などを付言事項として記載することで、相続人の心の整理をサポートすることが期待できます。
遺留分を把握した結果、どうしても一部の相続人の遺留分を侵害してしまう場合は、相続人に自分の意見を素直に伝え、納得してもらうことで相続トラブルを回避できる場合もあります。
遺言書を残す理由や想い、財産の相続について、生前からある程度、遺言者の口から話しておくことで、相続人の心の整理がつくかもしれません。必ずしもトラブルを回避できるとは限りませんが、相続人を納得させる機会になると思います。
遺言で一部の相続人の遺留分を侵害しているケースで、遺留分侵害額請求されると思われる場合は、遺留分侵害額請求されても困らない対策を行っておくといいでしょう。遺留分侵害額請求への対策には次のようなものがあります。
生命保険金は、原則的に遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、遺留分の対象にもなりません。特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、その相続人を受取人にした生命保険を活用するといいでしょう。ただし、生命保険金を受け取った相続人とそれ以外の相続人との間で著しい不公平が生じる場合は特別受益として持ち戻しの対象になるケースもあります。
推定相続人から被相続人へ虐待や重大な侮辱などがある場合、家庭裁判所に「廃除の申立て」を行うことで、その相続人の相続権を失わせることができます。正当な理由があり、一部の相続人へ遺産を渡したくない場合の選択肢の1つになりますが、必ずしも認められるものではありませんので、検討する場合には専門家へ相談しましょう。
A.法定相続人(兄弟姉妹以外)が遺留分の権利を持っています。遺留分を侵害された場合には、他の相続人に対して侵害された遺留分に見合う金額の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
A.遺留分侵害額請求の期限は「遺留分があることを知った時から1年」と「相続が発生してから10年」になっており、この期限を過ぎると遺留分侵害額請求を行う権利を失ってしまいます。
A.自筆証書遺言でも問題ありませんが、できる限り「公正証書遺言」で作成したほうがいいでしょう。もし、一部の相続人により遺留分侵害額請求が行われる場合、遺留分侵害額請求の前に「遺言無効の訴え」が行われる可能性があります。
自筆証書遺言書の場合は「本当に被相続人より作成された遺言書なのか」「遺言能力があったのか」が問題になる可能性がありますので、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
遺言書がきっかけで家族の仲が悪くなることは、遺言を残す人にとってとても辛いことだと思います。自分の相続に対する想いを実現しつつ、できるだけ家族で揉めないようするためには、遺留分に配慮した遺言書を作成することが大切です。
当事務所は、相続税対策などの生前対策のご相談も承っております。遺言書作成についてのご相談にも対応しておりますのでご検討の際は、以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
