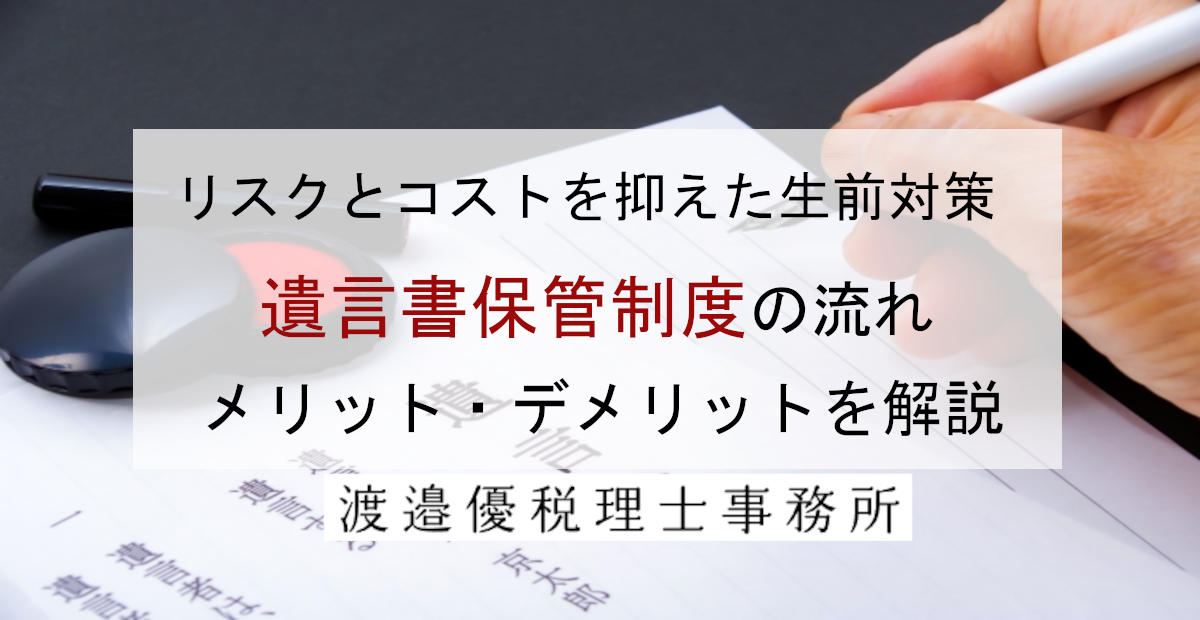
相続時のトラブルを未然に防ぐために生前対策として「遺言書の作成」が効果的です。遺言書では、相続人の間で遺産の分け方を指定したり、相続人以外へ財産の贈与を行ったり、婚外子の認知などを行うことが可能です。
一般的に利用される遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類あり、長所と短所があります。
自筆証書遺言には、自分で手軽に作成できる反面、遺言書自体を見つけてもらえなかったり、法的な要件を満たしておらずに無効になってしまったりするリスクがあります。公正証書遺言は、紛失したり、無効になったりしない確実な方法ですが、相続財産の金額に応じた公証人への手数料が発生します。
遺言書の作成を検討している方の中には「自分が作成した遺言書は確実に見つけてほしいけど、費用をあまりかけたくない」という方も多くいると思います。その方にぴったりな方法が「遺言書保管制度」です。
ここでは、少ないコストでできる生前対策「遺言書保管制度の流れ、メリット・デメリット」を解説します。
目次
遺言書保管制度とは、2020年7月より運用が開始された「自筆証書遺言を法務局で保管してくれる」制度です。これまで自筆証書遺言がある場合でも、簡単に見つけられない場所に遺言書が隠されており、遺言書が発見されないリスクがありました。遺言書保管制度を利用することで、紛失のリスクはもちろん、第三者に改ざんされる心配もありません。
遺言書保管制度の簡単な流れは次のとおりです。
①~③は、相続が発生する前の手続きになっており、④は相続発生後に相続人が行う手続きになります。
有効と認められる自筆証書遺言の作成を行います。要件を満たさないと無効になってしまうおそれがありますので注意して作成しましょう。
遺言書の保管申請書を作成し、保管申請の予約を行います。予約した日時に指定した遺言書保管所へ行き、手続きを行います。指定できる遺言書保管所と必要書類は次のとおりです。
【指定できる遺言書保管所】
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
【保管申請に必要な書類】
・遺言書(ホチキス止めはしないまま)
・保管申請書(様式は法務局のHPでダウンロード)
・住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入りのもの。コピー不可)
・運転免許証、マイナンバーカード等(顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
・手数料3,900円(収入印紙で納付)
問題なく手続きが終了すると「保管証」が交付されます。保管証に記載されている保管番号は、保管した遺言書を特定するための重要な番号ですので大切に保管しましょう。
遺言書は、保管している遺言書の閲覧や遺言書の保管の申請を撤回、住所などの変更の届出を行うことができます。遺言者が生存している間は、遺言者以外の人は保管されている遺言書を閲覧することはできません。
遺言者が亡くなった後、相続人は遺言書保管所へ予約を行い「遺言書保管事実証明書の交付の請求」「遺言書情報証明書の交付の請求」「遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求」を行うことができます。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認するための書類であり、遺言書の内容を確認できるものではありません。
「遺言書情報証明書の交付の請求」は、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。「遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求」は遺言書の内容を確認するために行う手続きです。
【各申請に共通して必要な書類】
・交付請求書(様式は法務局のHPでダウンロード)
・戸籍(除籍)謄本など(遺言者が死亡したことを確認できる書類)
・請求者の住民票の写し
・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
・運転免許証、マイナンバーカード等(顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
・手数料(収入印紙で納付)
「遺言書情報証明書の交付の請求」「遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求」には、上記の書類に加えて以下のチャートに応じた書類が必要になります。
提出した書類に問題がなければ、申請した証明書を受け取ることができます。相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付、遺言書の閲覧を行うと、遺言書保管官はその人以外の相続人に対し、遺言書を保管している旨の通知を行い、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
遺言書保管制度には次のようなメリットがあります。
自筆証書遺言書には、自筆で全文を書くことや作成した日付を正確に自筆で書くこと、氏名を自筆で書くこと、印鑑を押すことなど、形式的な要件があります。この要件を満たしていなければ遺言書は無効となり、法的な効力を持ちません。
遺言書保管制度では、法務局が要件を満たしていない遺言書を預かることはできず、形式面でのルールについてのチェックが行われます。このチェックにより、遺言書が無効になるリスクを回避することが可能です。
ただし、法務局で行われるチェックは形式のみであり、遺言書の内容に関する相談を行うことはできません。
通常の自筆証書遺言の場合、遺言書を発見した人または相続人が遺言書を開封する前に家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらう「検認手続き」を行わなければなりません。検認手続きは、裁判所に申し立てを行ってから完了まで数週間から2か月程度かかるため、相続手続きを完了させるために時間がかかってしまうデメリットがあります。
遺言書保管制度では、法務局での遺言書の保管時に既に遺言書の存在が確認されており、形式面のチェックが行われているため、検認手続きは必要ありません。遺言書情報証明書の交付が行われた後、すぐに相続手続きを進めることができます。
遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言書のリスクの1つである「遺言書が発見されないこと」を回避することができます。遺言者は、相続人に「遺言書は法務局に預けてある」と言うだけで遺言書の有無と保管場所を伝えることが可能です。万が一のため、法務局から発行された「保管証」のコピーを相続人に渡しておいてもいいでしょう。
また、法務局では遺言者が指定した方への通知(指定者通知)にも対応しており、戸籍担当部が遺言者の死亡の事実を確認した場合に指定者へ遺言書が保管されていることのお知らせを行います。指定者通知を希望することにより、遺言者が遺言書の存在を一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも遺言書の存在を知らせることが可能です。
遺言書保管制度には、あまり大きなデメリットはありません。強いて言えば、本人が法務局に出向いて手続きを行う必要があり、保管時に3,900円の費用と住民票の写し等の取得に関する費用が発生する点です。
A.原則として15歳以上の年齢で遺言能力がある人であれば誰でも遺言書を作成することができ、遺言書保管制度を利用することができます。ただし、遺言書保管制度により遺言書の保管の申請ができるのは遺言者本人のみとなっており、本人が直接出向いて手続きを行う必要があります。
A.費用は1通3,900円の手数料となっており、遺言書の記載された財産の金額が多い場合であっても費用は変わりません。支払いは現金ではなく、収入印紙による納付になります。
A.遺言書の保管は撤回を申請することで遺言書の返還を受けることができます。新たに内容を変更した遺言書を作成し、保管申請を行うことで変更後の遺言書が有効になります。撤回をせずに新たな遺言書の保管を申請することも可能ですが、複数の遺言書が存在することになってしまうため推奨されていません。
A.相続人に遺言書を預けたことを伝えておいたほうがスムーズに手続きが進みます。できれば「保管証」に記載してある「保管番号」を伝えておくことをおすすめします。保管証は紛失すると再発行できませんので、大切に保管するようにしましょう。
遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のデメリットをなくし、少しの費用で確実に遺言書が相続人のもとへ届くように考えられた制度です。「自筆証書遺言は発見されるか心配」という場合には、ぜひ検討してみましょう。
ただし、保管制度のチェックでは遺言の中身の相談はできませんので、弁護士や税理士などの各種専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所は、相続税対策などの生前対策のご相談も承っております。遺言書作成についてのご相談にも対応しておりますのでご検討の際は、以下の問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
Contact us
お問い合わせ・無料相談のご予約
オンライン面談可(平日10:00-18:00)
平日夜間・土日は有料(1回につき1万円)
受付時間 10:00~18:00(月〜金)
